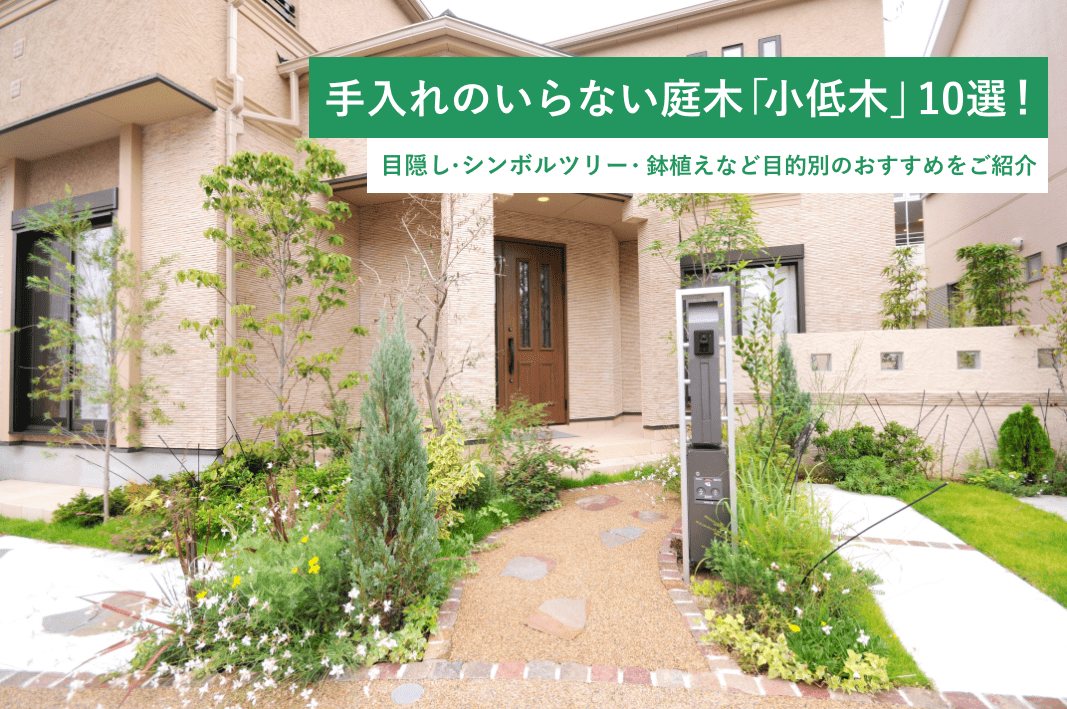手入れのいらない庭木をお探しであれば、お勧めしたいのが小低木です。成長がゆっくりで剪定などの作業が少なく、簡単に管理できます。
この記事では、小低木の種類や選び方のほか、庭づくりのコツについて解説していきます。シンボルツリーや目隠し、生垣などに小低木を使いたいとお考えの方や、和モダン・イングリッシュガーデンなどのおしゃれな庭を目指している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
小低木・低木とは?手入れのいらない庭木におすすめする理由

低木とは、成長した際の高さが約3m以下の木を指し、その中でも高さが約1m以下のものは「小低木」と分類されます。
これらの庭木は成長スピードが比較的ゆるやかで、大きくなりすぎない種類が多いため、剪定の頻度が少なくても美しい樹形を保ちやすく、手入れが簡単なのが特徴です。
特に小低木は樹高が低く管理しやすい一方で、目隠しにはあまり向きません。逆に、ある程度の高さが出る低木は、生垣や目隠しとして利用されることが多く、用途によって選び分けるのがおすすめです。
手入れのいらない庭木の特徴と低木・小低木のメリット、選ぶときのポイント
初めて庭づくりをする、という方にとって手入れのいらない庭木はありがたい存在です。ここでは特に管理がしやすい低木・小低木の特徴と、選ぶ際に気をつけたいポイントをいくつかご紹介します。常緑樹か落葉樹かによっても異なる特性を持つため、しっかりとそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
手入れのいらない庭木の特徴を知る

庭木には低木や高木などさまざまな品種があり、それぞれに異なる特徴があります。中には、剪定などの手入れの頻度が少なく、維持管理の手間があまりかからない樹木も存在します。ただし、植物である以上、成長しますし、時には病気にかかることもあるため、「一切手入れが不要」というわけではありません。
それでも、できるだけ手間をかけずに庭木を楽しみたいという方は、まず「どのような特徴を持つ庭木であれば手間が少なくて済むのか」を知ることが大切です。たとえば、次のような特徴を持つ樹木は、比較的手入れが楽だと言えるでしょう。
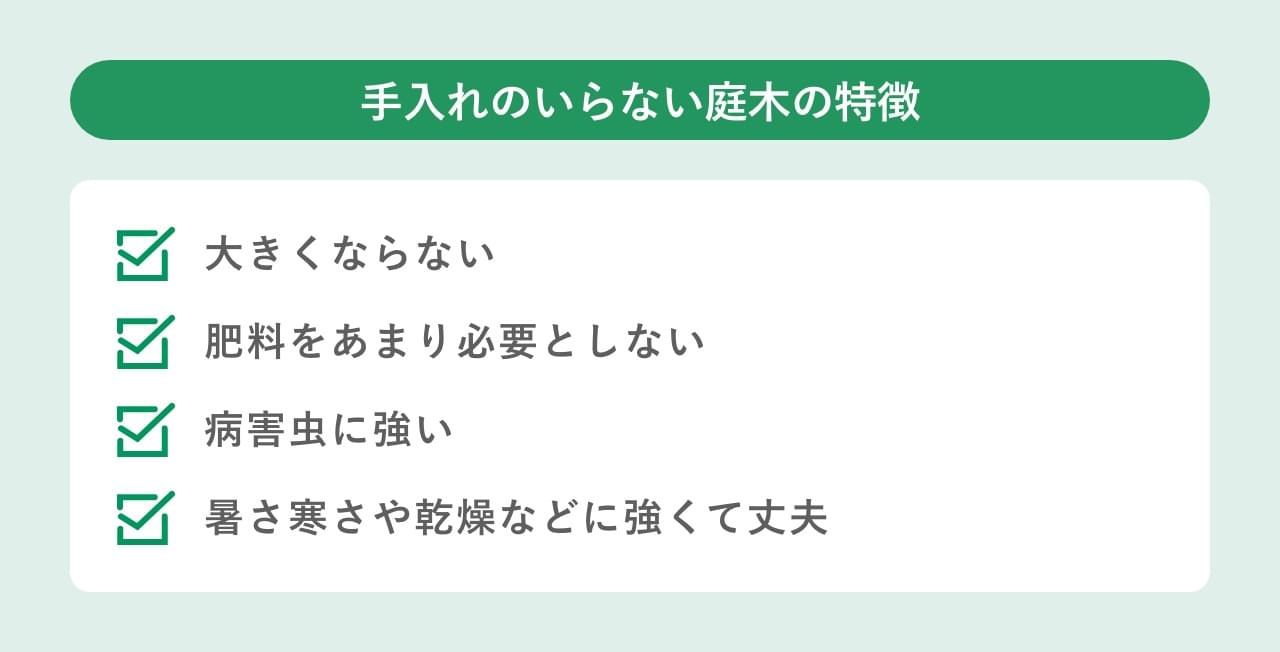
■大きくならない庭木
成長スピードが遅く、あまり大きくならない小低木などは、剪定の頻度が少なくて済むため、手入れのいらない庭木としてお勧めです。
何mにも成長する樹木の場合、庭から道路へはみ出した枝を剪定するだけでも、脚立を使ったり、長い剪定ばさみを用意したりと手間がかかります。
その点、大きくならない木は手が届きやすく、剪定が必要になった際にも手軽にお手入れできるのが利点です。
■肥料をあまり必要としない庭木
植物を元気に育てるには定期的な肥料が必要ですが、品種によってはそれほど肥料を必要としないものもあります。
そのような庭木を選べば、肥料を与える手間が減るだけでなく、追肥のタイミングを見極めるためにこまめに樹木の状態を確認する必要もなくなり、管理がぐっと楽になります。
■病害虫に強い庭木
病気にかかりにくく、害虫の被害を受けにくい小低木なども、手間のかからない庭木といえるでしょう。
こうした丈夫な庭木であれば、病害虫の予防や対策のために薬剤を散布したり、傷んだ枝を剪定したりする手間を大幅に省くことができます。
■暑さ寒さや乾燥などに強くて丈夫な庭木
手入れのいらない庭木を選ぶなら、耐暑性・耐寒性があり、乾燥にも強い丈夫な品種がお勧めです。
暑さや寒さに弱い庭木の場合、お住まいの地域や季節によっては弱ってしまったり、枯れてしまったりすることもあります。特に寒さに弱い品種は、気温が下がる時期に「冬囲い」の作業が必要になることも。
その点、環境の変化に強く、丈夫に育つ庭木なら、そうした手間も少なく済みます。
常緑樹・落葉樹のメリット・デメリットを知って選ぶ

手入れのいらない庭木として小低木や低木を選ぶ際は、常緑樹にするか落葉樹にするかを検討することも重要です。ここでは、常緑樹と落葉樹それぞれの特徴と、メリット・デメリットをご紹介します。
■常緑樹のメリット・デメリット
常緑樹のメリット
-
一年中緑を楽しめる
-
手入れが比較的楽
-
丈夫で育てやすい
常緑樹のデメリット
-
庭が重たい印象になりやすい
-
寒さに弱い品種がある
-
植える場所に注意が必要
常緑樹とは、1年を通じて葉を茂らせる樹木のことです。新芽が出る際に古い葉が落ちることはありますが、一度に葉が落ちることはないため、落ち葉の掃除が比較的楽なのが特徴です。また、常に葉がついていることから、目隠しとしても適しており、冬でも緑を楽しめるため、庭が寂しい印象になりません。さらに、常緑樹には成長が緩やかで、暑さや乾燥に強い低木も多く、手入れの少ない庭木をお探しの方にもお勧めです。
ただし、葉の色がやや暗めで密に茂るため、庭全体の雰囲気が重く感じられることがあります。また、寒さに弱い品種もあるため、植える際は日当たりの良い場所を選ぶなど、環境への配慮も必要です。
■落葉樹のメリット・デメリット
落葉樹のメリット
-
四季の変化を楽しめる
-
明るい雰囲気をつくりやすい
-
花木としても楽しめる種類が多い
落葉樹のデメリット
-
落ち葉の掃除が大変
-
目隠し効果が冬に失われる
-
管理場所に注意が必要
落葉樹とは、秋に紅葉し、冬になると葉を落とす樹木のことです。四季の移ろいを感じられる庭にしたい場合には、落葉樹がお勧めです。葉が一気に落ちるため、樹形を整えるための剪定の手間が省けるというメリットがあります。明るい色の葉をつける種類が多く、庭の雰囲気も明るく爽やかになります。また、美しい花を咲かせる種類も多く、手入れの少ない花木をお探しの方には、落葉樹の低木をチェックしてみるのも良いでしょう。
ただし、落葉樹は紅葉後に一気に葉が落ちるため、落ち葉の掃除が大変になる時期もあります。掃除のしやすさを考慮して、植える場所を選ぶことが大切です。また、葉を落とすと目隠しとしての役割がなくなるため、生垣には不向きです。さらに、落葉樹には成長が早く、暑さや乾燥に弱い種類が比較的多いため、半日陰など涼しい場所に植えるなど、やや手間がかかることもあります。
目的にあわせて低木を選ぶ(シンボルツリーや目隠し、おしゃれ、鉢植え)
手入れのいらない庭木として低木や小低木を取り入れたいと考えている場合は、シンボルツリーや目隠し、鉢植えなど、目的に応じて選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの用途に適した低木の特徴をご紹介します。
シンボルツリーにするなら

シンボルツリーは、お家や庭の“顔”となる樹木です。エクステリアのアクセントになるだけでなく、目隠しとしても活躍します。成長スピードが遅い低木であれば、こまめな剪定が不要なため、美しい樹形を保ちやすく、「手入れのいらないシンボルツリー」を探している方にもお勧めです。
低木の中でも、常緑樹は一年を通して葉がついているため、目隠しとして使いたい場合に向いています。
一方、落葉樹は紅葉や花が楽しめる品種も多く、四季の変化を感じたい方にぴったりです。また、シンボルツリーを植える玄関先・中庭・大きな窓の前などのスペースや、日当たりの条件に応じて、適した樹木を選ぶことも大切です。
なお、おすすめのシンボルツリーについては、以下の記事でもご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
「【シンボルツリー12選】おすすめの人気庭木と選ぶときのポイント」
目隠しにするなら

家の外からの視線が気になるときや、防犯対策をしたいときには、生垣などによる目隠しが効果的です。低木を植えて家の周囲を囲んだり、隣家との境界線に沿って植えたりすることで、自然でおしゃれな目隠しを実現できます。コンクリート塀で囲うと圧迫感が出やすいですが、植栽を使えば柔らかくナチュラルな雰囲気に仕上がります。
目隠し用の庭木としては、一年を通して葉をつけている常緑樹がお勧めです。特に、目線の高さまでの樹高があり、枝や葉の密度が高い品種を選ぶと、季節を問わず安定した目隠し効果が期待できます。
ただし、植え付けた直後は枝葉が少なく、目隠しとしての効果が十分に得られない場合もあります。そのため、成長の早い常緑低木を選ぶと、比較的短期間で目隠しとして機能するようになります。
おしゃれに見せたいなら

せっかく庭づくりをするなら、見た目にもおしゃれに仕上げたいですよね。そんなときは、庭全体に「テーマ」を持たせてみるのがお勧めです。
たとえば、手入れが楽な常緑の低木を使いながら「落ち着きのある和モダンな庭」や「イングリッシュガーデン風のナチュラルで華やかな庭」など、テイストに合わせたデザインを楽しむことができます。
あらかじめテーマを決めておくことで、どんな種類の低木を選べばよいかが明確になり、植栽計画もしやすくなります。また、手入れのしやすい低木を中心に寄せ植えしながら、適度に中低木や高木を取り入れると高低差が出て、より立体感のある自然な庭に仕上げることができます。
鉢植えで管理できるものは

あまり大きくならない庭木であれば、鉢植えで育てるのもお勧めです。鉢植えは置き場所を気軽に変えられるため、西日の強い季節だけ半日陰に移動したり、シンボルツリーや目隠しとしての配置を変えたりと、自由なレイアウトが楽しめます。また、鉢植えで管理すれば土の量を調整できるため、木が大きくなりすぎるのを防ぐことも可能。限られたスペースでも庭木を楽しめる方法として人気があります。
鉢植えに適した庭木を選ぶ際は、成長が早いものや根が深く張るタイプは避けましょう。鉢の中で根が詰まりやすく、樹木に負担がかかって枯れてしまうことがあります。そのため、ゆっくりと成長する低木が鉢植えには適しています。
おすすめの手入れのいらない常緑樹と落葉樹を紹介
手間のかからない庭づくりにぴったりの低木・小低木の庭木を、常緑樹・落葉樹に分けてご紹介します。花や実で季節の彩りを楽しめるだけでなく、剪定や肥料の手間が少なく、初心者でも扱いやすい品種ばかりです。鉢植えで管理できるものも多いため、スペースの限られた庭やベランダにもおすすめです。
鉢植えで管理できるものは
■コトネアスター

コトネアスターは、秋に小さな赤い実をたくさんつける姿が美しい常緑低木です。葉にはツヤがあり、ナチュラルな雰囲気で、庭先や玄関まわりにもよくなじみます。
手入れはとても簡単で、伸びすぎた枝を整える程度の剪定で十分。病害虫にも強いため、「虫がつきにくい低木を植えたい」という方にもおすすめです。
樹高:0.3~2m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:日当たりと水はけの良い場所
■ツツジ

日本原産のツツジは日本の環境で育てやすい低木です。約4,000以上の種類があるといわれ、常緑性と落葉性に分類されます。常緑性ツツジの代表的な種類には、キリシマツツジやクルメツツジなどがあります。赤やピンクの鮮やかな花が4~5月にかけて咲き、庭を華やかにしてくれるでしょう。
丈夫な性質で美しい花が咲くのが魅力ですが、生育条件が合わないと病虫害を受けやすいので、多くの品種の中から環境に合うものを植えるのがポイントです。
樹高:0.5~2m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:日当たりの良い場所・水はけの良い酸性土
■ジンチョウゲ

ジンチョウゲは春に良い香りの花を咲かせる常緑性の低木で、「日本三大芳香木」の1つです。自然と丸みのある樹形に育つため、基本的に剪定不要なのが特徴となっています。花が咲く低木で手入れのいらない庭木を探している方にはぴったりです。
根が地中深くまで伸びないため乾燥には注意が必要で、成長期の春や高温になる夏は水やりを忘れないようにしましょう。
樹高:1~2m
耐暑性・耐寒性:普通
栽培環境:西日の当たらない半日陰・水はけの良い土
■カルミア

カルミアはコンペイトウのような蕾がかわいらしい常緑低木です。開花すると傘のような花が楽しめ、地植えでも鉢植えでも栽培できます。
剪定をしなくても自然に樹形が整うので、手入れのいらない庭木としてお勧めです。ただし、夏の暑さや乾燥には弱いため、夏は寒冷紗で遮光するなどして直射日光を避けて管理しましょう。
樹高:1~3m
耐暑性:やや弱い 耐寒性:普通
栽培環境:西日の当たらない半日陰・水はけの良い酸性土
■ビバーナム

ビバーナムは常緑ガマズミとも呼ばれ、横に広がる樹形が特徴の常緑低木です。目隠しや生垣として使いやすく、手入れの少ない庭木を探している方にお勧めです。
春には白い花が咲き、初夏には赤い実をつけ、秋には紅葉も楽しめるなど、一年を通して季節の変化を感じられるのが魅力。花つき・実つきも良く、自然と樹形が整うため剪定の手間もほとんどかかりません。
樹高:2~3m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:日当たりと水はけの良い場所
落葉樹
■シモツケ

シモツケは春~初夏にピンクの小花を咲かせ、秋には紅葉を楽しませてくれる低木の落葉樹です。落葉樹ならではの季節によって変わる姿が魅力で、丈夫なので初心者でも育てやすいでしょう。
あまり大きくならないため剪定も少なくて済みますが、花が終わったあとに切り戻すと形が整うとともに、翌年も花がきれいに咲きます。和風・洋風どちらの庭木としても馴染みやすい万能な品種です。
樹高:0.5~1m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:日当たりと水はけの良い場所
■シロヤマブキ

シロヤマブキは春に白い花を咲かせる落葉性の低木です。ヤマブキの花に似ていることから、その名前がつけられました。
暑さ・寒さに強く、初心者でも育てやすい品種ですが、乾燥に弱いため、夏の強い西日が当たる場所は避けるのがポイントです。自然に樹形が整うためこまめな剪定は不要ですが、枝が古くなると花がつきにくくなるため、落葉期に古い枝や枯れた枝を切り取りましょう。
樹高:1~2m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:西日の当たらない半日陰・水はけの良い土
■ミツマタ

ミツマタは2~3月にかけて花を咲かせる落葉低木で、枝が3つに分かれることからその名前がつきました。可愛らしい黄色い花が一般的ですが、オレンジがかった赤い花を咲かせる品種もあります。咲いたときにはふんわりと甘い香りが漂い、春の訪れを感じさせてくれます。
自然と樹形が整って丸い形になっていくので、剪定の手間が少なくて管理しやすいです。日なたから明るい日陰まで割と幅広い場所で栽培できますが、夏の強い西日は避けるようにしましょう。
樹高:1~2m
耐暑性:強い 耐寒性:普通
栽培環境:日なた~明るい日陰・水はけの良い肥沃な土
■ヒュウガミズキ

ヒュウガミズキは春に黄色い花をたくさん咲かせる落葉性の低木です。枝いっぱいに花がうつむいたようにして開花します。花のついた枝を切り、花瓶に挿して室内で楽しむこともできるのでお勧めです。
枝が細かく分かれながら自然と丸く整った樹形になるため、剪定の手間がほとんどかかりません。また、刈り込みにも強いことから、生垣としても利用しやすく、庭のアクセントや目隠しとしても活躍してくれます
樹高:2~3m
耐暑性・耐寒性:普通
栽培環境:日当たりと風通しの良い場所
■クロモジ

クロモジは、枝や葉に爽やかな香りを持つ落葉性の低木です。春になると、黄色の小さな花を咲かせ、自然な風情を楽しませてくれます。樹皮に見られる黒い斑点が文字のように見えることから「クロモジ」と名づけられました。香りの良さから、お茶やアロマオイルの原料としても人気があり、皮つきの楊枝に使われることでも知られています。
自然と樹形が整うため剪定の手間は少ないですが、枝葉が混みあってきたら落葉期に剪定するのがお勧めです。また、低木の中ではやや樹高があるため、シンボルツリーとしても活用しやすい品種です。
樹高:2~3m
耐暑性・耐寒性:強い
栽培環境:西日の当たらない日当たりの良い場所~半日陰・水はけの良い肥沃な土
庭木を剪定して手入れするときのコツ

前述のとおり、手入れのいらない庭木といっても、まったくメンテナンスが必要ないというわけではありません。枝が伸びすぎて道路や隣家にはみ出したり、樹形が崩れて見た目が悪くなったり、枯れた枝が目立ってきたりした場合には、剪定による手入れが必要です。
剪定には、目的に応じて以下の3つの種類があります。
- 切り戻し剪定:庭木の高さや広がりを抑えるために行う剪定
- 透かし剪定:混み合った枝や枯れ枝を取り除いて風通しや見た目を整える剪定
- 花がら摘み:咲き終わった花を切り取って次の花つきを促す剪定
庭木の状態をこまめにチェックしながら、必要に応じて適切な剪定を行うことで、長く美しい姿を保てます。ここからは、そんな剪定を行う際に知っておくと便利なコツをご紹介します。
剪定ばさみは消毒してから使う
剪定ばさみを使う際は、枝の切り口から細菌が入り、庭木が病気になることを防ぐために、あらかじめ消毒しておきましょう。塩素系漂白剤を100倍に薄めたものでつけ置きする方法や、アルコールスプレーで拭き取る方法が有効です。特に、病気になっている庭木を剪定した後に他の木を切る場合は、病気が移らないように消毒が欠かせません。
一度に3分の1まで剪定してOK
庭木をどのくらい剪定してよいか迷う方は多いでしょう。そんなときは、樹木の高さあるいは枝全体の本数の「3分の1」までを目安にすることをお勧めします。この割合までであれば、剪定しても問題ありません。
また、数回カットするごとに1歩後ろへ下がって樹木全体を見ると、樹形のバランスがわかり、次にどこを切るべきか判断しやすくなります。剪定する量に迷ったら、大きく切るのではなく、少しずつ小さく切っていくのが失敗しないコツです。
不要な枝を見つけて剪定しよう
庭木をすっきりさせたり、枯れた枝を取り除いたりする「透かし剪定」では、不要な枝を選んで切り取ります。どの枝を切るべきか知っておくと、剪定時に迷うことがなくなります。
主に以下のような枝が不要な枝です。
- 枯れた枝
- 細くて弱々しい枝
- 内側や下向きに伸びた枝
- 複数の枝が重なっている部分
- ひこばえ(木の根元から生える新しい枝)
これらの不要な枝を剪定することで、木は新しい芽を出すためのエネルギーを有効に使えるようになります。
枝を切る際は、ハサミの入れ方にも注意が必要です。枝を斜めに切ると切り口の表面積が大きくなりますが、まっすぐに切ることで表面積を小さくできます。これにより、剪定後の庭木がより早く回復します。
低木を使ったおしゃれな庭づくりのコツ
前述のとおり、低木でおしゃれな庭にするなら、イングリッシュガーデンや和モダン風など、テーマを決めるのがお勧めです。それぞれのテーマで庭をつくるときのポイントを紹介します。
イングリッシュガーデン風にするコツ

洋風の庭づくりで人気のイングリッシュガーデンは、四季折々の花や、さまざまな高さの庭木を使って、自然の風景のようなナチュラルな雰囲気を楽しむのが特徴です。庭が狭かったり日当たりが悪かったりしても作りやすいため、日本でも広く取り入れられています。
そんなイングリッシュガーデンで低木を使うなら、高木との組み合わせがお勧めです。樹高3m以上の高木をシンボルツリーに選び、低木と組み合わせることで、高低差や奥行きのあるおしゃれな植栽になります。
たとえば、斑入りの葉が特徴的なシルバープリペットや、ハーブとしても使えるギンバイカ(マートル)は、イングリッシュガーデンの低木として定番です。これに合わせる高木としては、オリーブやミモザ(アカシア)などがシンボルツリーとして人気です。
植物だけでなく、ナチュラルな小物を取り入れるのもポイントです。木製のテーブルやベンチ、ブリキや鉄製の置物、石やレンガなどを使って、庭全体をコーディネートしましょう。テラコッタやブリキ、天然木を使った鉢植えを庭のあちこちに置くのもお勧めです。
鉢植えの素材やデザインにこだわれば、ベンチなどを置くスペースがなくても、鉢植えそのものがナチュラルな雰囲気を演出してくれます。大きくならない木や目隠しになる木を鉢植えにすることで、庭のコーディネートにも馴染みやすくなるでしょう。
和モダン風にするコツ

和モダン風の庭づくりでは、庭木の種類にこだわることが大切です。特に、紅葉する落葉樹は日本の四季を感じさせ、和の雰囲気にぴったりです。花や実がなる木を選ぶことで、季節の移り変わりを楽しめます。
庭に奥行きを出すには、シンボルツリーとなる高木を1本植え、その周りに低木を組み合わせるのがお勧めです。たとえば、美しい樹形のイロハモミジや、花が魅力的なヤマボウシ、ハナミズキなどは、和風の庭によく馴染み、シンボルツリーとしても最適です。
植物だけでなく、石や砂利、苔などの素材も活用すると、一気に和の雰囲気が高まります。飛び石や景石を配置したり、砂利を敷いたりするほか、手水鉢やししおどしなどで水を取り入れると、さらに趣のある空間になります。
手入れのいらない小低木を目隠しやシンボルツリーにしよう
今回は、手入れのいらない庭木の特徴や、おすすめの低木・小低木について紹介しました。
あまり大きく育たない庭木は、剪定などの管理が楽に行えるのが大きな魅力です。
また、常緑樹と落葉樹それぞれの特徴を把握したうえで、庭に植える樹木を選ぶことも重要です。
これから家を建てておしゃれな庭をつくりたいとお考えの方は、ぜひ手入れのいらない小低木の庭木を取り入れてみてはいかがでしょうか。
庭だけでなくお家の中でも植物を楽しみたい方は、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。
「初心者から始めるエアプランツ!おしゃれな飾り方と失敗しない育て方とは?」
公開日:2025年09月29日
RECOMMENDおすすめ記事はこちら
Hana
建築・インテリアの大学を卒業後、大手家具メーカーに勤務。現在はインテリア・ライフスタイルの専門ライターとして活動中です。10年以上にわたりさまざまな植物の栽培を楽しんでおり、その経験を活かした園芸テーマの執筆も行っています。